フードバンクオキナワ基金
沖縄では、経済的な困難を抱える家庭やひとり親世帯、そして、子どもの居場所づくりに取り組む団体も、日々「食」への不安を抱えています。近年は物価の高騰が家計を直撃し、これまで以上に生活の負担が増している現実があります。私たちの活動は、そのような方々が安心して暮らせる地域づくりを行っています。
企業や個人から提供された食品を必要としている人々へ届けることで、生活と安心を支えるとともに、食品ロスという社会課題にも向き合い、「もったいない」を「ありがとう」に変える循環型の社会づくりをめざしています。地域で支え合う仕組みを育みながら、誰ひとり取り残さない社会を目指して、活動を続けています。

私たちNPO法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄は、「もったいない食品」を地域で必要としている方々へ届けることで、地域社会の課題に向き合い、持続可能な社会づくりに取り組んでいます。
代表である奥平は、テレビで食品ロスの現状を知り、「まだ食べられるのに捨てられてしまう食品」を知り大きな衝撃を受けました。そして同時に、その食品を福祉施設などに届ける「フードバンク」の存在を知り、「自分にもできることがある」「沖縄にも広めたい」と強く感銘を受けたことが、活動のはじまりです。
2007年当時、沖縄にはまだフードバンクの仕組みがなく、企業や食品会社からの寄付を得ることも、福祉団体へ届けることも簡単ではありませんでした。奥平はまず、活動を知ってもらうことから始めました。何度も断られながらもチラシを手にフリーマーケットで呼びかけを続け、やがて「ここで食品を集めてみては?」という声が寄せられ、フリーマーケット会場が初めての食品寄付の場となりました。
その小さな一歩から、活動は大きく広がりました。企業や地域の福祉施設からの協力が増え、個人や学生ボランティアが食品を集めて持ち寄ってくださるようになりました。さらに行政とも連携し、生活に困窮する方々への食品提供の窓口ができるまでに成長しました。今では、多くの方々の善意と行動が集まり、沖縄のフードバンク活動の力強い原動力となっています。
この活動は、皆さん一人ひとりの支えがあってこそ続けられます。ご寄付は、困難な状況にある方々の「今日の一食」となり、地域全体の希望につながります。これからも、多くの方に「食べられることの安心」を届けるために、私たちは活動を続けていきます。
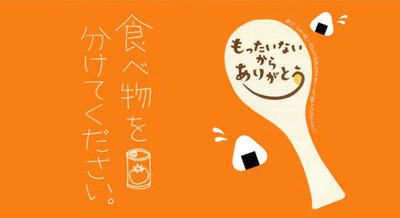
フードバンクセカンドハーベスト沖縄は、行政の支援だけでは届かない地域の方々に、民間の立場から食品を届ける活動をしています。企業や個人から寄付された食品を無償で受け取り、品質管理をしながら、必要とする人たちに安全に届けています。
現在は、離島を含めた県内約130か所の子どもの居場所や社会福祉協議会、行政などと連携し、食品の利用を各地で行ってもらっている他、ひとり親家庭などに直接食品を支援する「フードパントリー」にも取り組んでいます。
これらすべての活動は、寄付や助成金によって支えられています。ご寄付は、食品の保管や運搬、拠点の維持などに大切に活用し、地域の「食の支え合い」を広げる力となっています。

沖縄県は、全国でも相対的貧困率が高い地域であり、とくに子どもを抱える家庭の貧困が深刻な課題となっています。加えて、近年の物価高騰や新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活に困窮する世帯が増え続けています。一方で、まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品も多く存在しています。このような背景から、食を通じた支援の必要性はますます高まっており、社会全体で課題解決に取り組むことが求められています。

私たちの活動は、多くの協力者と地域資源に支えられています。食品を提供してくださる企業・農家・個人のみなさまはもちろん、各地域で活動する福祉団体や子ども食堂、行政機関、そしてボランティアスタッフの存在が欠かせません。また、公益財団法人みらいファンド沖縄の仕組みを活用し、寄付を募る基金を設置することで、地域の方々が活動に参加できる環境を整えました。活動の様子をSNSで発信し、できるだけ見える活動と関係づくりを大切にしながら、地域全体で支え合うネットワークを広げています。

2007年の設立以来、フードバンクセカンドハーベスト沖縄は地道に地域での活動と信頼関係を重ねてきました。最初はわずかな食品寄付の始まりでしたが、現在では年間100トン規模の食品を受け入れ、今では年間約40万人以上の方々に支援を届けるまでに成長することができました。
今後も行政や福祉団体との連携も強化し、災害時の緊急支援にも対応できる体制を構築しています。また、食品の品質管理や安全な保管や配送のために冷蔵設備の導入を進めるなど、食品を快適な状況で届ける環境づくりにも取り組んできました。
これからも、沖縄県内で必要とされる「食のセーフティネット」を強化していくため、安定した活動資金の確保が不可欠です。特に、食品の保管・配送にかかる費用や、パントリー活動を継続するための運営資金の確保が必要です。
また、物価高騰や災害時にも迅速に対応できるよう、支援の拡充とネットワークの強化を目指すためにも、当法人の安定的な運営基盤構築が急務な課題です。皆さまからのご寄付は、こうした地域の支え合いを持続可能なものにする力となります。ともにこの活動を支え、誰もが安心できる地域を築けるお力をお貸しください。

※(公財)みらいファンド沖縄を通じた本基金へのご寄付は、税制優遇の対象です。詳細はこちら
※本基金への寄付額のうち15%を(公財)みらいファンド沖縄の基金運営費に充当させていただきます。

・子ども達のお弁当で5キロのお米は1週間持たないし、物価高騰でお米も高くなっているのでお米の提供はとても助かります。子ども達にたくさん食べさせてあげられます。(連携先からの食品利用者)
・食費が高くなり、収入は変わらず生活費を圧迫して困っていました。本当に助かりました。(連携先からの食品利用者)
・大人から子どもまでワクワクするような食品を用意していただき、毎月とても楽しみにしています。(パントリー利用者)
・フードバンクは、これからの時代とても必要です。(パントリー利用者)
・お⽶の提供が⽣活の安⼼につながり、この活動のおかげで助かった世帯は数知れません。
・お⽶があることで届け先にも⽀援する側にも、安⼼感が⽣まれました。
・食品を支援したことにより、子どもたちとの信頼関係が生まれ、⼦どもたち⾃ら相談を切り出すきっかけになりました。


