CASE02
寄付と助成のプログラム「たくす」
専門医から病院の垣根を超えた患者会へ継続寄付 基金の活用で寄付の受け渡しがスムーズに
寄付先 : 乳がん患者が「元気に乳がんと闘う」ための環境づくりプロジェクト
募集主:NPO乳がん患者の会ぴんく・ぱんさぁ
寄付者 : 医師
NPO乳がん患者の会ぴんく・ぱんさぁは、活動開始19年目(2024年3月現在)を迎えたNPOです。2005年に病院の垣根を越えて患者同士がサポートし合う自助グループとしてスタートし、5年後の2010年には浦添に常設の拠点「ぴんく・ぱんさぁリボンズハウス」を開設。専門家による講演会や乳がん検診の受診啓発活動など、さまざまな形での情報発信とネットワーキングに取り組んでいます。
クラ目-1-scaled-1.jpg)
病院の垣根を超えた患者会を発案
ぴんく・ぱんさぁの代表を務める与儀淑恵さんは、2001年にご自身が乳がんに罹患し、専門医である宮良球一郎医師とつながりを持ったことから患者会の立ち上げに至りました。

患者同士が集えることが病気に立ち向かう力になる
「退院後に、入院していた時の仲間で食事会をした時、宮良先生が来てくれたのです。そこで、術後の痛みや痒みなど不安なことについて先生に尋ねたりする中で、皆が似た悩みを抱えていたことに気づき、不安が和らぎました。中には、先生が各地で開催していた勉強会に情報を求めて通い詰めている人もいました。患者や元患者どうし話をすることで、こんなに力をもらえるならば、自分達だけじゃなくて他の人たちにも場を広げたいという思いを持ち、患者会をつくる動きが始まりました」
宮良医師から「ゆくゆくはNPOにしてはどうか」と提案があり、与儀さんたちは那覇市NPO活動支援センターを訪ねます。そこで、乳がんの患者会に類する活動がないことや、助成金を取得するためのセミナーが開かれることを知りました。
「セミナーのワークショップで、自分達は何がしたいのか、何ができるのかを模造紙に整理できました。それを宮良先生に受け取ってもらって。また、セミナーの時に那覇市NPO活動支援センターさんから『助成金の公募に応募してみては?』とご提案いただいたんです。手術したばかりだった私には無理だと思ったのですが、周囲の皆さんの熱い声援に背中を押されてなんとか書類を作成。締め切りの日に、仲間が届けてくれて、助成金が下りました」
与儀さんは、この経緯を通じて那覇市NPO支援センターを運営していた現みらいファンド沖縄代表理事の小阪亘と知り合い、以後、さまざまな相談をお寄せくださっています。
法人化の検討と取りやめから基金の創設へ
与儀さんは、当初から検討課題だった「NPO法人にするかどうか」についても、小阪に相談いただきながらメリット・デメリットを整理。「患者会がない病院にかかっている患者も、病院の患者会に入っていない患者も活動に入れるようにしたい」「治療にお金がかかっているので会費は取りたくない」「乳がんであることを隠している人がほとんどで名簿を集めることも難しい」「元気になったら活動を離れて生活に戻ってもらいたい」といった指針を整理する中で、法人化して事務作業負担などのコストがかかる状態になると、やりたいことができないのではないかという結論に至りました。
そうするうちに、与儀さんは夫の転勤で北大東島への転居が決まり、患者会の活動は那覇市NPO支援センターの私書箱を使って続けることになりました。
「活動を続けるうちに、『与儀さんいますか?』とNPO支援センターを訪ねてくる方が出てきました。来たい人に会えるような体制にしたいと考え、てんぶす那覇(当時の那覇市NPO支援センター所在地)のピロティにいてみようかな?とか、自宅を連絡先として公開しようか?と思案していたところに、宮良先生から『クリニックの向かいのアパートにずっと空室があるから見てみたら?』とご連絡をいただいたのです。さらに『家賃と光熱費を出してあげるから拠点をつくっては』との申し出もいただき、活動を始めて5年目にして、大きく状況が動き始めました」
与儀さんたちは、宮良医師の申し出に対して「とてもありがたいけれど、お金を出していただくのは心苦しい」という思いを持っていました。そんな折、県外で認定NPO法人として活動する患者会の方と情報交換をする中で「認定NPO法人になれば、寄付をしてくださった方が税制優遇を受けられる」と耳にし、再度法人化を検討しました。ですが、やはり法人化に伴う負担が活動の妨げになる状況に変わりはありません。そこで小阪に相談をいただき、みらいファンド沖縄が提供する「寄付と助成のプログラム」の仕組みを使って基金を創設することで、法人化することなく優遇税制が適用される手立てを整えることにしました。
「小阪さんから基金の仕組みについて伺ったとき、ぜひお願いしたいと思って申請しました。宮良先生にもご説明いただき、『先生にもメリットがあるなら、私たちも気持ちが楽です』とお伝えし、先生からも『いいよ、応援するよ』と快諾いただきました」
こうして、拠点の開設が決定。「開設にあたって、宮良先生は『僕はお金は出すけれど口は出さないから』とおっしゃり、一つだけ約束事を提示されました。それは、『どの病院の患者さんでも平等に使える場所にしてほしい』ということでした」そこで与儀さんたちは、患者会が運営する拠点の先行事例「しんゆりリボンズハウス」を見学しました。
しんゆりリボンズハウスは、がん患者のためのサロンの全国ネットワーク「キャンサーリボンズ」のひとつです。キャンサーリボンズは、全国に21(2024年4月現在)の拠点があり、多くは病院を軸に医師や看護師によって運営されています。加盟することで各地のリボンズハウスの活動から多くを学べると感じたことから、与儀さんたちは拠点をリボンズハウスとして始めることを決めました。
こうして「ぴんく・ぱんさぁリボンズハウス」が誕生。それ以来、乳がんに罹った人やその家族が体験者の声を聞きに訪れることのできる「心の拠りどころ」として活動を続けています。
みらいファンド沖縄を活用 ①公益法人格
みらいファンド沖縄は「公益財団法人」の法人格を持つ財団です。公益に資する働きを全うし、市民の皆様から集めた寄付金などを不当に内部留保していないことなどを、毎年の監査により沖縄県知事から認められています。このことにより、みらいファンド沖縄を通した寄付に対しては優遇税制が適用されます。ぴんく・ぱんさぁは、みらいファンド沖縄を「装置」として介在させることで、宮良医師の応援の気持ちがこもった寄付金を、宮良医師にもメリットのある形で受け取り、リボンズハウスの運営・維持に生かしておられます。
ぴんく・ぱんさぁリボンズハウスを開設、善意の循環の場に
2023年に開設13年を迎えたぴんく・ぱんさぁリボンズハウスは、宮良先生の言葉どおり、病院の区別なく相談したい人が集まるピアサポートサロンとして、さまざまな形で活用され続けています。
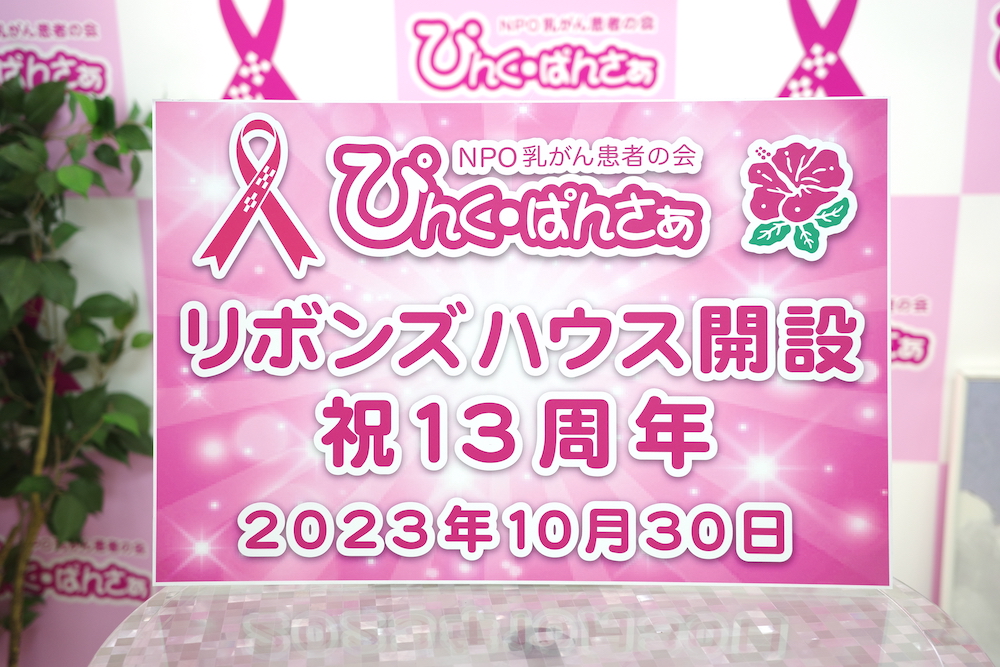
「ある日突然、診断を受けて乳がんの当事者になった人にとって、相談相手を見つけることは簡単ではありません。身の回りの人には隠しておきたい気持ちを持つ人も少なくありません。どうしたらいいかわからず不安な気持ちを抱えて、みなさん直接ここに来ます。『誰に伝えるべきか。同じ境遇に置かれた人はどうしているんだろう?』『先生は、仕事は辞めなくていいというけれど、本当に大丈夫?』『ひととおり説明を受けたけれど、何がわかっていないかがわからなくて不安』などなど、当事者同士でしか話せないことがあります」
命に関わることについては「治療方法の選択については正解を決めつけない」という基本を守りつつ、「先生にこんな質問をしてみたら?」「セカンドオピニオンを取るという方法があるよ」といったアドバイスはしているそう。また、常駐している与儀さんがご自身の経験から答えられることを答えるだけでなく、境遇が似ている経験者に来てもらうなどのマッチングもしています。
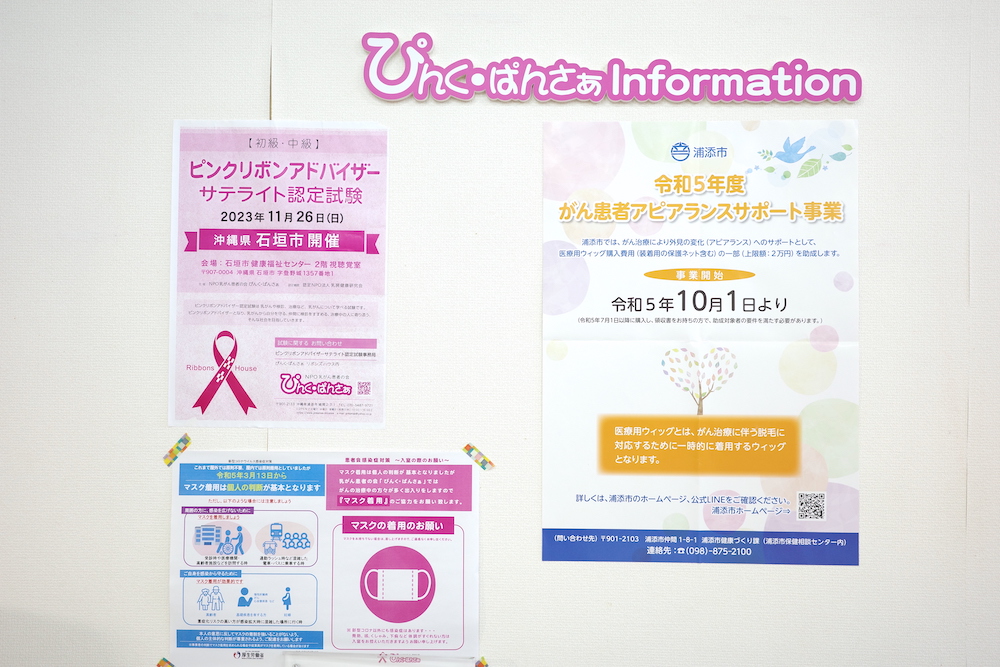
さまざまな情報提供やピンクリボンアドバイザーの養成も手がける
相談相手になれるならと、「電話番号を教えてもいい」と申し出る元患者が現れるなど、関わり始めたときには患者として支えられる側だった人が寛解してから支える側になることも多く、リボンズハウスという拠点がハブとなって善意の循環が起きています。

有志のメンバーが実体験から考案し手作りした帽子
「開設した当時、私たちは患者というだけで素人でした。ところが、この場所ができたことでいろいろなプロフェッショナルが集まってきてくれるようになりました。告知を受けてうつ状態になり、ここへきてぼーっと『どうしたらいいでしょう。元気になれるかな』と言いながら通っていた琉舞の先生が、2-3年後に元気になって、ここで教えて下さったりイベントの時に出てくださったこともあります。他にも、ラジオ番組を持っている方がイベントを企画してくださったり、手芸が得意な方が抗がん剤で髪の毛が抜けてしまった時の気持ちに寄り添った帽子を編んでくださっていたりもします。」
また、企業や団体の慈善事業の受け皿としても機能しており、与儀さんは、拠点があることの力を身にしみて感じていると言います。
アドバイザーの養成や企業とタイアップした啓蒙活動も
与儀さんたちはまた、リボンズハウスを拠点に、多くの取り組みを実施してきました。

ANA SPORTS PARK浦添で、ライトアップを活用した啓蒙活動を実施
「相談相手になる方が寄り添い方を学べるよう、琉球大学病院のがんセンター内にある沖縄県地域統括相談支援センターが実施している『がんピア・サポーター養成講座』の受講を推奨し、サロンでは自主勉強会を開催しています。また、乳がんを正しく理解して健診を勧めたり、治療やその後の生活をサポートする目的で認定NPO法人乳房健康研究会が認定する「
他にも、琉球ゴールデンキングスが『KINGS LADIES DAY』を開催。アリーナ内のLEDビジョンを使った啓発や、キングスダンサーズのパフォーマンスによるピンクリボン運動を展開し、ぴんく・ぱんさぁの活動を支援しています。
みらいファンド沖縄を活用② 相談
与儀さんは、ANA SPORTS PARK浦添でのライトアップを浦添市の助成金20万円を獲得して実施しました。20万円では足りないという事態に陥った時に、小阪に相談くださり、ご紹介したまちづくり会社と連携を取ることで活動趣旨への共感を得て、足りない予算分をライトアップイベントの事務局側が負担することに。モニュメントをピンク色にライトアップしたことでNHKの取材も入り、啓蒙活動を成功させました。与儀さんは「何か困ったことがあると小阪さんに電話します」と話しておられ、基金だけではなく、みらいファンド沖縄に蓄積したさまざまなリソースを存分に活用して下さっています。
「これだけやっていて法人にしていないの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、法人にしていないからこそ、したい活動に注力できていると思っています」と話す与儀さん。活動の源には、当事者として向き合った辛い気持ちや状況をネガティブなものとして終わらせるのではなく、未来をつくる種にして生かしていく心意気があります。
「乳がんになった時、お金も時間もかかるし、苦しいし、悩むし、痛い思いもしました。『なんでがんになってしまったのか?』と意味を考えたときに、得たものに目を向けたいと思いました。私が乳がんを宣告された頃は、マンモグラフィーが普及し始めたばかりで、見落とされてしまうことも珍しくない時代でした。『乳がんが感染る』なんていうデマを信じている人もいて、面と向かって言われた患者もいました。誰が悪いのではなく、時代の流れの中のそこにいた私だったという経験を、知り合えた仲間と一緒に伝えていきたいと思っています。それが、女性たちの武器やエネルギーになればいいのかな」
みらいファンド沖縄は、発見されていなかった課題を見つけ、沖縄で暮らす人の選択肢が広がる活動に取り組むみなさまに、市民の資源をつなぐ装置を目指しています。NPO乳がん患者の会ぴんく・ぱんさぁ様の活動はまさに、病院の垣根を越えて乳がん患者どうしが助け合える場所がなかった沖縄を、そういう場所がある沖縄に変えました。これからも、乳がんの宣告を受けた方の心の拠り所があり続ける沖縄であるために、継続してお役立ていただきたいと願っています。
(聞き手:浅倉彩)



